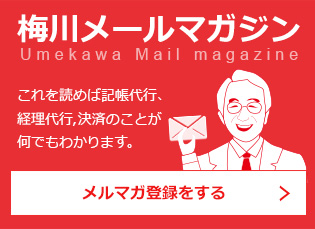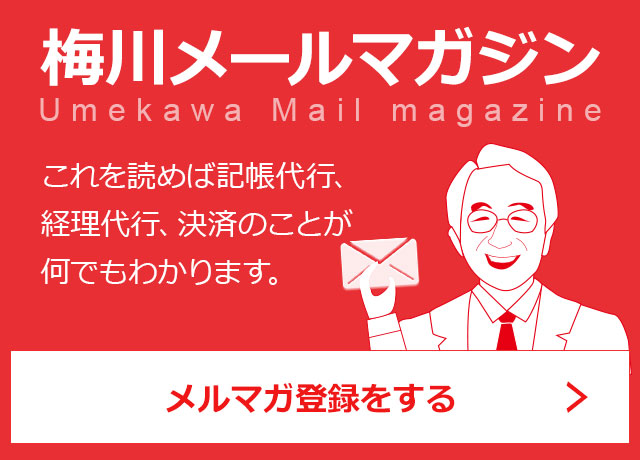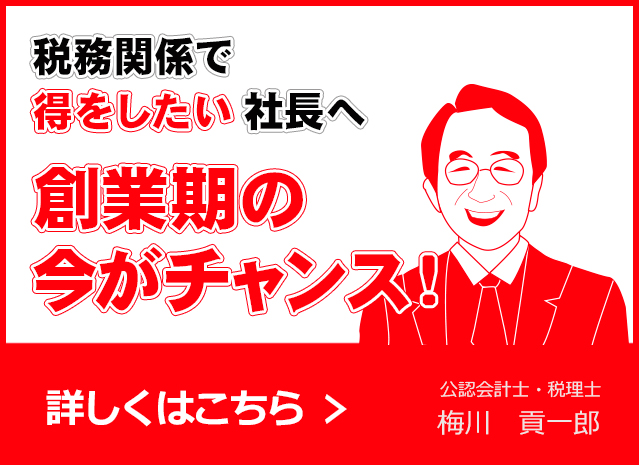飲食店経営のポイントは
- HOME >
- 会社の経営とは 一覧 >
- 飲食店経営のポイントは
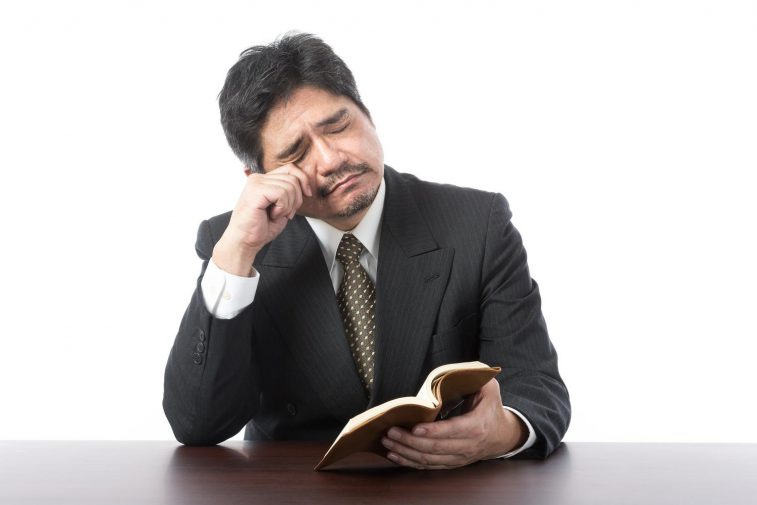
1. 厳しい飲食店の経営
総務省の調査によると、飲食店の店舗数は1991年をピークに毎年減少しています。
しかしその間、大手チェーンの店舗数が増加していることを考えると、中小営の個人飲食店はかなり減っていると考えられます。
出店、退店数を見ると、一年間で約5万店が増え、一方6万店が減っているといわれています。つまり1万店ずつ減っているということです。
さらに新規開店した飲食店のうち約7~8割が、開業後3年後閉店に追い込まれています。
開業後3年間で生き残っているのが2~3割。10年後生き残っている飲食店は1割です。
今後日本の人口は減少の一途をたどります。生活費に占める外食費の割合も減少しており、飲食業は、超激戦を戦わなくてはなりません。
現在、年間で6万店もの飲食店が閉店に追い込まれている一方では、黒字店の平均利益率が10~20%といわれるなか、100%以上の利益率を稼いでいる繁盛店も存在します。
この差はどこから来るのでしょうか。
一言でいうと、飲食業は、他の業種に比べてあまりに無計画であり、数字を無視しています。いわばどんぶり勘定であり、数字に基づいた分析、対策が全くできていません。
経理や財務の数字に対しての無理解やミスは営業努力を簡単に吹き飛ばします。
飲食店の経営者が営業努力をしていないとは決して言いません。
メニューの開発や売上アップのアイディア、接客態度の向上、しかし前述のような現実に対してそんな抽象的な対策ではお店は救えません。
2. 飲食店成功のポイントは
実は、飲食業を成功させるポイントは2つしかありません。
お客様を魅了する独自のこだわりコンセプトを持つ
数字に強くなる
コンセプトとは営業的に成功させるために不可欠なもので、お店の経営スタイルや、こだわり、接客スタイル、店舗デザインに至る一つのまとまった考え方です。
「数字」で大切なのは、お店の売上や支出をしっかり把握していること。
特に重要なのは、「投資金額に対する利回り」と「FLRコスト」の二つです。
なぜなら、利回りは収益性と投資の回収率を現すものであり、飲食業では3大コストである、F=原価、L=人件費、R=家賃で収益性が決まってしまうからです。
これは、一般に言われるような原価を30%以下にしなければならないというものではありません。前述したように重要なのはお店のコンセプトです。そのコンセプトによりそれぞれの割合は異なります。
しかし共通して言えるのは、FLRの合計コストを70%以内にするということです。
立ち食い寿司は、F原価を落としてはいけません。その代りLはパートさんを活用するなど工夫してできる限り低くします。
逆に高級クラブのようなお店では、Fは関係ありません。このようなお店でおいしいものを食べようという人はいません。勝負はL、接客のしっかりできる美人をそろえる必要ありそこにコストを惜しんではいけません。
FLRの比率を70%とする場合、仮に利益率を10%を見込むならば、残りの経費は20%に抑えなければなりません。光熱費、販促費、通信費などその他の費用は20%を超えてはなりません。
常にFRLコストを意識して、お金の使い方を意識していれば大きく失敗することはありません。
3. 損益分岐点とは
飲食業の数字の管理でもう一つ重要なのが、損益分岐点管理です。
損益分岐点とは、最低いくら売上なければ利益が出ないという売上ポイントです。
経費は、売上高に応じて増減する変動費、原材料費やパートさんの給料、水道光熱費などがあります。また、売上高に関係なく一定額かかってくる固定費、家賃、リース料、銀行返済金、正社員の月給などがあります。
経費を固定費と変動費に分解することによって損益分岐点を算出することができます。
これは、必要な利益を設定してそれに必要な売上高、目標売上高を算定するのに必要です。
多くの飲食店では、利益を結果と考えています。
これでは、いつまでたってももうかりません
まず、必要な利益を設定します。
そのためには、うちのFLRコストの構造、すなわちコンセプトでは最低いくらの売上を実現しなければならないかを決定します。
さらには、そのために限られた予算の範囲でいかに売上高を達成すればよいかを考えます。
コンセプトを決定したら、目標とする利益の金額を決定してそのための売上高を目指すのが成功への道筋です。
もう一つ、簡単ですが多くの飲食店がやっていないのがメニューごとの原価の計算です。
製造業では、製品原価が命です。製品原価を正確に把握していないと製品価格も決定できませんし、どの製品を主力にするかも決定できません。
しかしなぜか飲食業では、原価に無頓着です。
原価率が高くもうからないメニューを一生懸命売ってその結果赤字を膨らませている例をよく見かけます。
飲食業における製品原価は、工業製品のように複雑に考える必要はありません。
要は、材料費の合計だけで十分です。
それを100グラム単位、500グラム単位で計算すれば十分です。
これが価格決定の基本になります。
場合によっては、原価を下回る売価の設定も必要かもしれません。しかしこれを戦略的に行うのか、結果としてそうなるかでは天と地ほどの差があります。
トータルとして平均の原価率を達成するための値段設定が必要です。
原価の計算は休みの一日を費やせば必ずできます。
このわずかな努力がお店の利益につながるのです。
4. 月次決算をご存知ですか
飲食業で絶対必要なのが、月次決算です。
月次決算とは、月の売上と経費を集計していくら儲かったか。現預金はいくら増えたか、原価率は何%だったか、来客一人あたりの売上はいくらだったかという一か月の経営の結果を数字で集計することです。
飲食業の一つの特徴は、環境変化に対して敏感であるということです。
飲食業の経営者は、その環境変化に対して常に対応策を打っていく必要があります。
それは最低でも一か月に一回は行わなければなりません。
対応が遅れるとお客様はあっという間にいなくなります。
原価の集計は時間がかかりますが、売り上げの集計は毎日できます。
少なくとも売上の変化は毎週集計して検討することが必要です。
今月の必要売り上げを実現するためには今週何をするべきか、キャンペーンの実施か、新しいメニューの投入か、常にアンテナを張り巡らせて考えなければなりません。
そのためにも数字の把握はなるべくクイックに対応は素早くが原則です。
5. リピート客はたくさんいますか
飲食店では、来店客の平均7割が新規のお客様、3回以上来店したリピート客は3割といわれています。
売上を伸ばすには、新規のお客様を増やすかリピートのお客様のリピート率を高めるしかありません。
これはそれほど難しい課題ではありません。
私は、月に最低1回は訪れるお気に入りのお店が5店はあります。
だいたい普通ではないでしょうか。
いつも新しいお店を探すという面倒なことはしません。
その選ばれた5店に入ることができれば十分生き残ることができます。
それもちょっとした努力です。
お店のコンセプトをはっきりと打ち出すことと、ちょっと面倒かもしれませんが数字に基づいた科学的な経営管理を行うこと、それだけで絶対あなたのお店は繁盛します。
このブログを一通り読めば、あなたの不安は少し解決できるかもしれません。ただし記事数が多いので、一気に読むのは時間の問題もあり難しいかもしれません。ちょっとした空き時間に読むなど、学びのペースメーカーとして、メルマガを活用して下さい。内容は次の通りです。
- ・最新の記事や、必読記事のご案内。
- ・無料セミナーや、特典レポートのご案内。

この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。