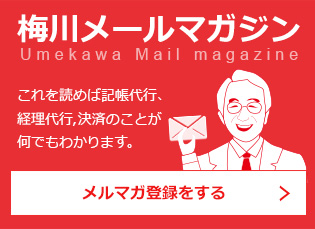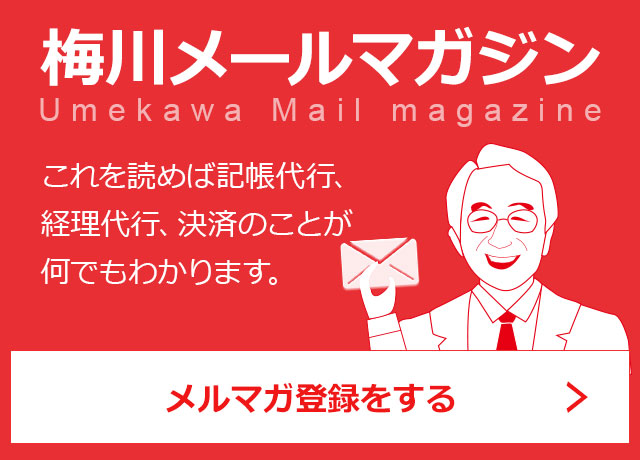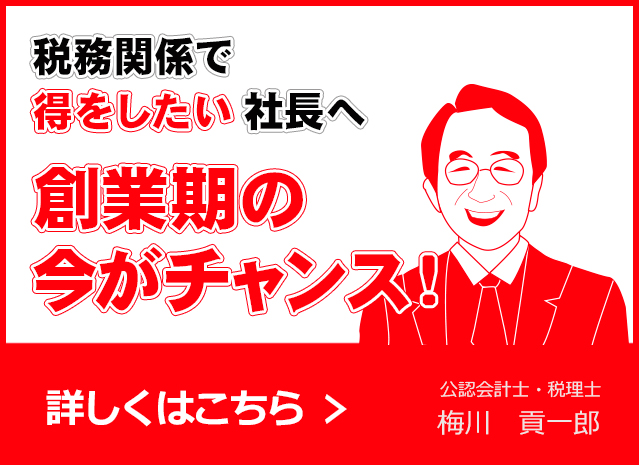領収書や請求書、帳簿などの書類の保存期限は
- HOME >
- 経理・決算・帳簿 一覧 >
- 経理の合理化 一覧 >
- 領収書や請求書、帳簿などの書類の保存期限は
![XIj5DSfdQwGstDqHSSR2_cab[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/XIj5DSfdQwGstDqHSSR2_cab1-1-757x426.jpg)
領収書や請求書、帳簿などの書類を何年保存しなければならないか?
実はよく聞かれます。
確かに取引量の多い業種や業態によっては保存しなければならない文書の量は膨大になります。
その保管場所を考えてもコスト(家賃)のかかる話ですしはっきり言って邪魔です。
日常の実務を考えれば、一年以上前の領収書や請求書を引っ張り出して見ることは稀です。
結論から言えば税務上、帳簿や領収書などの資料の法定保存期間は7年間です。
法律に詳しい方は、会社法上商取引の時効は5年でしょ。
また、税金の時効も5年だから、書類も5年保存でいいのではと思われるかもしれません。
ところが、税法では、不正、偽りがある場合には時効は2年間ストップして実質7年間さかのぼって徴税することができるのです。
しかし実務上7年間さかのぼることはまずありません。
少なくとも私は聞いたことがありません。
通常の税務調査では、3年間分調査します。
そこで脱税が発覚した場合5年間さかのぼる可能性は否定できません。
だからと言って、一応法律で7年間の保存を義務付けているので、さすがに5年間立ったからと言って資料を捨てるわけにはいきません。
私のお勧めは保存すべき書類が多い場合は、3年分を事務所内の手元に保存し4年から7年までのものをレンタル倉庫に保存するというものです。
後ろめたい申告をしてしまった方は、5年分手元に置いておいた方がいいかもしれません。
ところで、電子帳簿保存法という便利なものがあります。
あらかじめ税務署に届出を出しておけば、パソコンで作成した帳簿(総勘定元帳、仕訳帳など)を紙ではなくCDやDVDに保存しておくことができます。
取引の多い会社は、帳簿だけでも7年分と言えば相当な分量になります。
これをCDに焼いて保存できれば相当な合理化だと思います。
それでは、帳簿同様に、契約書、領収書や請求書もスキャナーで電子化してCDなどで保存してもよいか。
残念でした。
印鑑などが押されたり数字が手書きされた現物の資料は現物のまま保存しなければなりません。
ところで7年間保存というのは、税法上の保存期間です。
税法以外の各法律はそれぞれ独自の保存期間を定めています。
民法、会社法、労働法それ以外にもあるかもしれません。
なかには、「永久保存」なるものもあるようですから、それぞれ個別に調べる必要があるようです。
このブログを一通り読めば、あなたの不安は少し解決できるかもしれません。ただし記事数が多いので、一気に読むのは時間の問題もあり難しいかもしれません。ちょっとした空き時間に読むなど、学びのペースメーカーとして、メルマガを活用して下さい。内容は次の通りです。
- ・最新の記事や、必読記事のご案内。
- ・無料セミナーや、特典レポートのご案内。

この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

![photo-1446052377488-d40ee7263458[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1446052377488-d40ee72634581-1-362x242.jpg)

![photo-1437326584642-6019c5210de1[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1437326584642-6019c5210de11-1-362x241.jpg)
![photo-1430274173040-621f9174796b[2]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1430274173040-621f9174796b2-1-362x239.jpg)