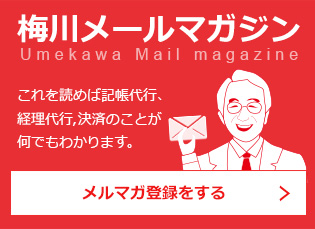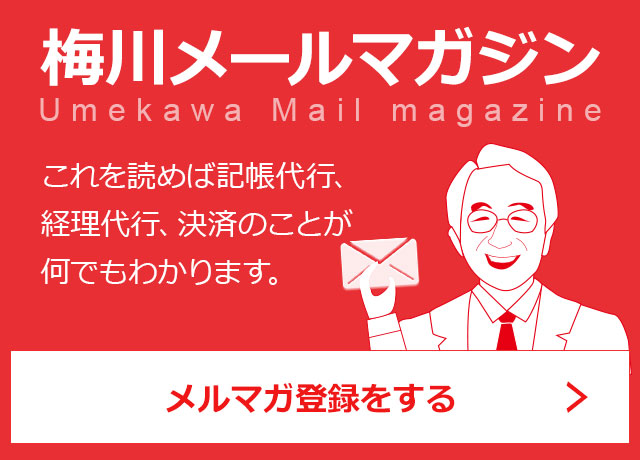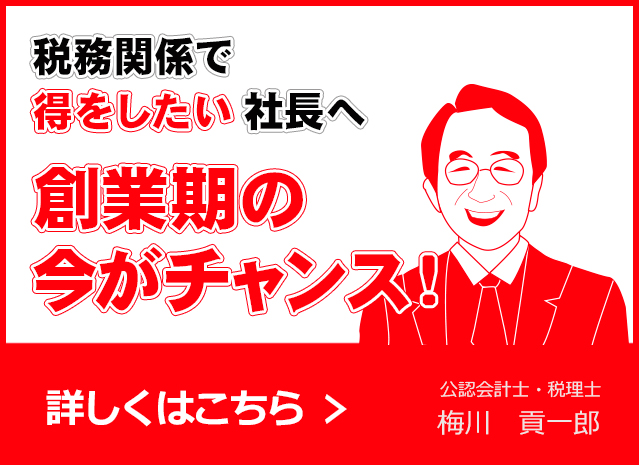税理士選びのコツ
- HOME >
- 税金の話 一覧 >
- 税理士の選び方 一覧 >
- 税理士選びのコツ

税理士選びのコツは何でしょうか。
その前に、そもそもなぜ企業は税理士と顧問契約をするのでしょうか。
社長は税理士に対して何を求めているのでしょうか。
この問いに対する答えが明確でないと、そもそも最適の税理士は選べません。
おなかが痛いのに眼科に行く人はいません。
実は税理士選びも一緒です。
この税理士は何ができるのか。
何が得意なのか。
実は、100人の税理士がいれば、その100人はそれぞれが固有の特徴を持っています。
ひたすら記帳代行と税務申告のみ行う税理士もいます。
個人の所得税を専門にする税理士もいます。
法人税は全く苦手、しかし相続税にはめっぽう強い税理士もいます。
節税が得意な税理士、税務調査に強い税理士。
実は税理士制度は、戦後そもそも税務署の退職者の再就職対策でできた制度と言われています。
税務署のOBが企業の納税のお手伝いをすることが税理士の趣旨です。
その効果は歴然で、登録している税理士の5割以上が税務署OBです。
意外かもしれませんが難しい税理士試験を合格した税理士は実は3割程度しかいません。
契約いている税理士がどのような資格で税理士登録をしているかは実は重要です。
難しい税理士試験を合格して税理士登録している税理士は間違いなく税法はくわしいです。
ただし、どの税目で合格したかは重要です。
受験する税金の課目は選択制ですので、比較的簡単な酒税や事業税、国税通則法などあまり実用に関係ない科目で合格している人もいます。
税務署OBの税理士を悪く言うつもりは全くありませんが、そもそも徴税を任務としていた人物が、突然立場を変えて企業の節税の指南をするとは考えにくいことです。
ただし、退職前に税務署長や副所長などの重要な官職にいた人は、退職後もそれなりの人脈による影響力を持っていることが想像できます。
事実、ある会社の税務調査では、有力なOB税理士に立ち会いを依頼したところ、交渉により指摘された追徴税金の金額が半分に減額されたという都市伝説があります。
大学院で税法を専攻していても税理士になることができます。
失礼ながら日本の大学院がさほど実務的な税務を教えるとは思えません。
私は公認会計士ですが、公認会計士は無試験で税理士登録することができます。
そして公認会計士試験では税法はほとんど勉強することないので、試験に受かったばかりの会計士はあまり税法を知りません。
私もそうでした。
その代り、会計士は上場会社の監査を経験していますから、会社の経営や取引の仕組み、経理体制、会社法など税法以外の周辺知識が豊富です。
このように一言に税理士と言っても、その生い立ちは様々。
知識、経験、専門分野も様々。
社長は自分の会社のニーズに合った税理士を選びましょう。
このブログを一通り読めば、あなたの不安は少し解決できるかもしれません。ただし記事数が多いので、一気に読むのは時間の問題もあり難しいかもしれません。ちょっとした空き時間に読むなど、学びのペースメーカーとして、メルマガを活用して下さい。内容は次の通りです。
- ・最新の記事や、必読記事のご案内。
- ・無料セミナーや、特典レポートのご案内。

この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。


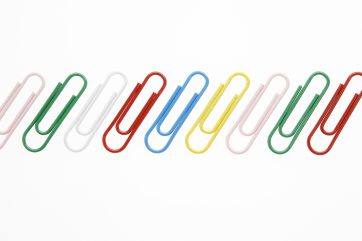


![photo-1462850932907-687c915e3d38[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1462850932907-687c915e3d381-1-362x241.jpg)
![yJl7OB3sSpOdEIpHhZhd_DSC_1929_1[3]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/yJl7OB3sSpOdEIpHhZhd_DSC_1929_13-1-362x242.jpg)
![photo-1449198063792-7d754d6f3c80[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1449198063792-7d754d6f3c801-1-362x241.jpg)
![photo-1443110189928-4448af4a2bc5[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1443110189928-4448af4a2bc51-1-362x303.jpg)
![photo-1430865254663-6d769b037f93[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1430865254663-6d769b037f931-1-362x241.jpg)