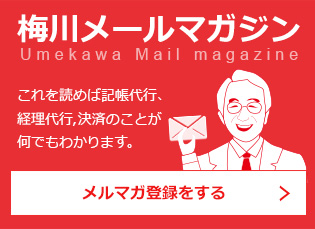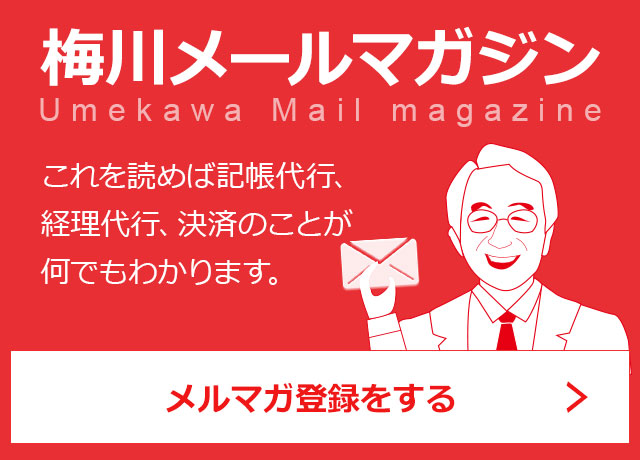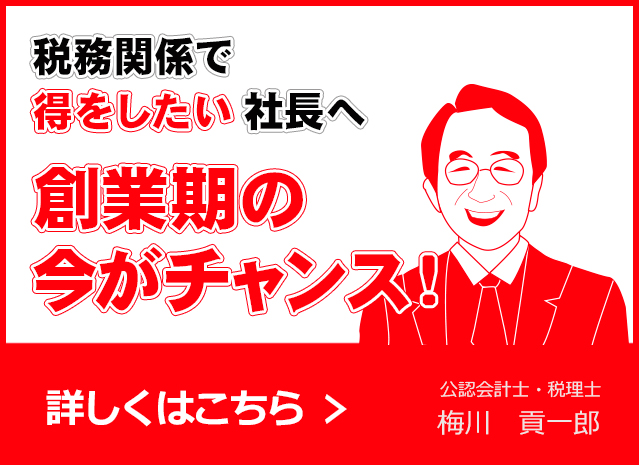貸借対照表は経営者自身です
- HOME >
- 経理・決算・帳簿 一覧 >
- 決算書の読み方 一覧 >
- 貸借対照表は経営者自身です

経営者の多くの方は、決算書、あるいは期中の残高試算表といえば損益計算書しか目を通さないようです。
貸借対照表は無視されているようですが、わかりづらいというのもあるのでしょうか。
せいぜい現預金の残高くらいしか確認しないようです。
私がお客様の決算書などを拝見する場合は、まず貸借対照表をじっくり見ます。
損益計算書から得られる情報よりも、貸借対照表から得られる情報のほうが圧倒的に多いですしその会社の社長の性格まで見て取ることができます。
損益計算書では、その会社の売上規模、粗利益率、営業利益あるいは経常利益の金額、税引き後利益の金額、各利益率くらいしか読み取れません。
それも今期のみの経営成績です。
ところが、貸借対照表は、その会社が設立以来今日に至るまでのすべての歴史が詰め込まれています。
設立後10年の会社であれば、その10年間のすべての会社の活動、経営者の意思決定の結果が凝縮されて数字に現れています。
売上高、利益が全く同じ同業者の会社であっても、貸借対照表は全く千差万別です。
ある会社は自己資本が10%程度しかない。
ほとんどの経営資産の調達が借り入れで賄われている。
一方では、借り入れがほとんど0。
過去の利益の内部留保で経営資源が賄われている会社。
過去にどのようなストーリーがあったのかまではわかりませんがいろいろ想像はつきます。
また、ある会社では同じ売上規模に対して商品・製品などの在庫が売上の2~3か月分と非常に多い。
一方では、半月分くらいしか置いていない会社。
在庫を多く持つかどうかは、経営判断にもよりますが、一般的には、倉庫のコスト、管理する人件費、購入するための資金、さらにその金利がかかるため、会社の財務体質は高コスト体質になります。
同様に売掛金の相対的に多い会社は、資金がそのぶん固定されるため、資金繰りが厳しくなりますし必要運転資金を借り入れに頼るのであれば借入依存体質になってしまいます。
どちらが好ましいかはもちろん自明のことです。
社長の意思決定は、損益計算書には比較的早く反映されます。
リストラを断行すれば、すぐに経費を減らすことができます。
ところが、貸借対照表を改善するのは一朝一夕にはできません。
時間をかけ、地道な努力を重ねないと素晴らしい貸借対照表はできないのです。
貸借対照表には社長の経営姿勢が見事に反映されます。
このブログを一通り読めば、あなたの不安は少し解決できるかもしれません。ただし記事数が多いので、一気に読むのは時間の問題もあり難しいかもしれません。ちょっとした空き時間に読むなど、学びのペースメーカーとして、メルマガを活用して下さい。内容は次の通りです。
- ・最新の記事や、必読記事のご案内。
- ・無料セミナーや、特典レポートのご案内。

この記事の執筆者
梅川公認会計士・税理士事務所 所長 梅川貢一郎
東京都千代田区を中心に活動。得分野は会社設立を含めた起業支援、創業融資、および創業期の企業向け経理・税務・会計サービス。

![XIj5DSfdQwGstDqHSSR2_cab[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/XIj5DSfdQwGstDqHSSR2_cab1-1-362x204.jpg)
![photo-1446052377488-d40ee7263458[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1446052377488-d40ee72634581-1-362x242.jpg)

![photo-1437326584642-6019c5210de1[1]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1437326584642-6019c5210de11-1-362x241.jpg)
![photo-1430274173040-621f9174796b[2]](https://www.umegawa.co.jp/magazine/wp/wp-content/uploads/2016/07/photo-1430274173040-621f9174796b2-1-362x239.jpg)